赤ちゃんが生まれてすぐに行うお宮参り。
そして、そのしばらく後に行う「お食い初め」の儀式。
子どもが一生食べるに困らないようにとの願いを込めて行います。
この「お食い初め」は、正式にはいったいいつ頃までに行いえばよいのでしょうか。
親の都合などで「お食い初め」の日にちを早めたり、遅くしてしまってもいいのでしょうか。
なかには、知らずにその時期が過ぎてしまった、という親御さんもいたりしますが。
果たして、過ぎてしまっても行って良いのなのでしょうか?
初めてのお子さんの場合は、親も何かと知識が不足していて、要領を得ないものですよね。
今回は、「お食い初め」の正式な時期や早めたり、遅くしても良いか、ということについての疑問に
お答えして行きたいと思います。
お食い初めの日にちは本当はいつまでにするべき?

お食い初めの時の献立には、一般的に「一汁三菜」を用意します。
「赤飯」に「焼き魚(鯛)」、「煮物」「香の物」そして「汁物」です。
で、これを誰が、食べるの?と聞きたくなります。
まさか、お父さんとお母さん?
そんなわけはありません(笑)
正真正銘、赤ちゃんのための祝い膳です。
でも、鯛や煮物なんて、幼稚園生でも苦手で食べられないというお子さんは沢山いそうです。
いったいこれをいつ準備するのでしょうか?
「お食い初め」は、正式には、そのお子さんが生まれた後「100日~120日」の間とされています。
つまり、4か月に入って、5カ月が来る前までに済ませるということですね。
この時期に、上記の様な祝い膳を用意して、
赤ちゃんの口元に持って行って、食べる真似をさせるのです。
その後、歯固めといって、歯が生える頃を無事迎えられた、
ということを祝し、
またこれから先もしっかり歯が生えるように、
との願いを込めて、
それ様の石を噛む真似をさせたり、
石につけたお箸をなめさせます。
生後4か月といえば、離乳食もまだの月齢です。
その時期にこうやって儀式をするんですね。
お食い初めの日にちは早めたり過ぎたりしていいの?
「お食い初め」の最も大切な意味合いは、
「一生食べることに困らないように」という願いを込めることです。
絶対に「100日目」でないといけない、ということはありません。
昔と今は違いますからね。
もちろん、「100日~120日」を過ぎて、遅れてしまっても大丈夫ですよ。
むしろ、京都では「食い延ばし」といって、
あえて120日を超えてから行う地域もあるくらいです。
その方が、長生きできるのだとか・・・
また、日にちを早めたい場合も、みんなで集まれる日を優先しましょう。
最近ではお食い初めをやらない家庭も多いようですし、
あまり日にちにはこだわらず、確実にできる日にやるようにしましょう。
お食い初めってどうして100日目なの?
ところで、生後4か月といえば、離乳食もまだの月齢です。
いくらなんでも早すぎると思いますよね。
もっと、あとでも良いのでは?
なんて思いますが・・・
今でこそ、人生100年時代と言われていますが、
わずか100年前でも、寿命100年なんて天文学的に大きな数字でした。
約100年前、だいたい大正時代でも日本人の平均寿命は、男女とも40~42歳くらいでした。
今の半分かそれ以下です!
ましてや、このお食い初めが始まったであろう昔、昔・・・では、この数字はもっと低かったと想像できます。
平均寿命ということは、なんとなく大人まで成長して、命が尽きるまでの年数・・・
と考えてしまいがちですが、
そうではなく、小さなうちに亡くなってしまう赤ちゃんも含めての数字です。
昔は、10人兄弟も珍しくなかったほど、子だくさんの家が多かったのですが、
その大きな理由は、
生まれても大きく育つ前に、病気などで亡くなる確率が、うんと高かったからなのです。
それは、お食い初めが行われる生後わずか100日を迎えることだって、決して当たり前ではなかったわけですね。
跡取りを産み、育て上げるということは、まさに真剣勝負だったわけです。
元気で長生きして欲しい、一生食べるに困らぬ生活を送って欲しい、という親たちの切なる願いの証が、
この「お食い初め」なのです。
この大切な意味を日本人としては、しっかりと理解しておきたいものです。
お食い初めの日にち、早めたり遅くしたりまとめ
現代では昔と違って、
仕事などでお父さんが「100日目」では同席できない、
という場合だってありえますよね。
それよりむしろ、両親、さらにお祖父さん、お祖母さんもきちんとそろって、
みんなでワイワイ言いながらお祝いできる方が幸せでしょう。
正式には、食べる真似をさせるのは一族の最年長者がいいそうですから、
お祖父さんの膝の上にでも乗せてもらいながらお食い初めが出来たとしたら、赤ちゃんも本望でしょうね。




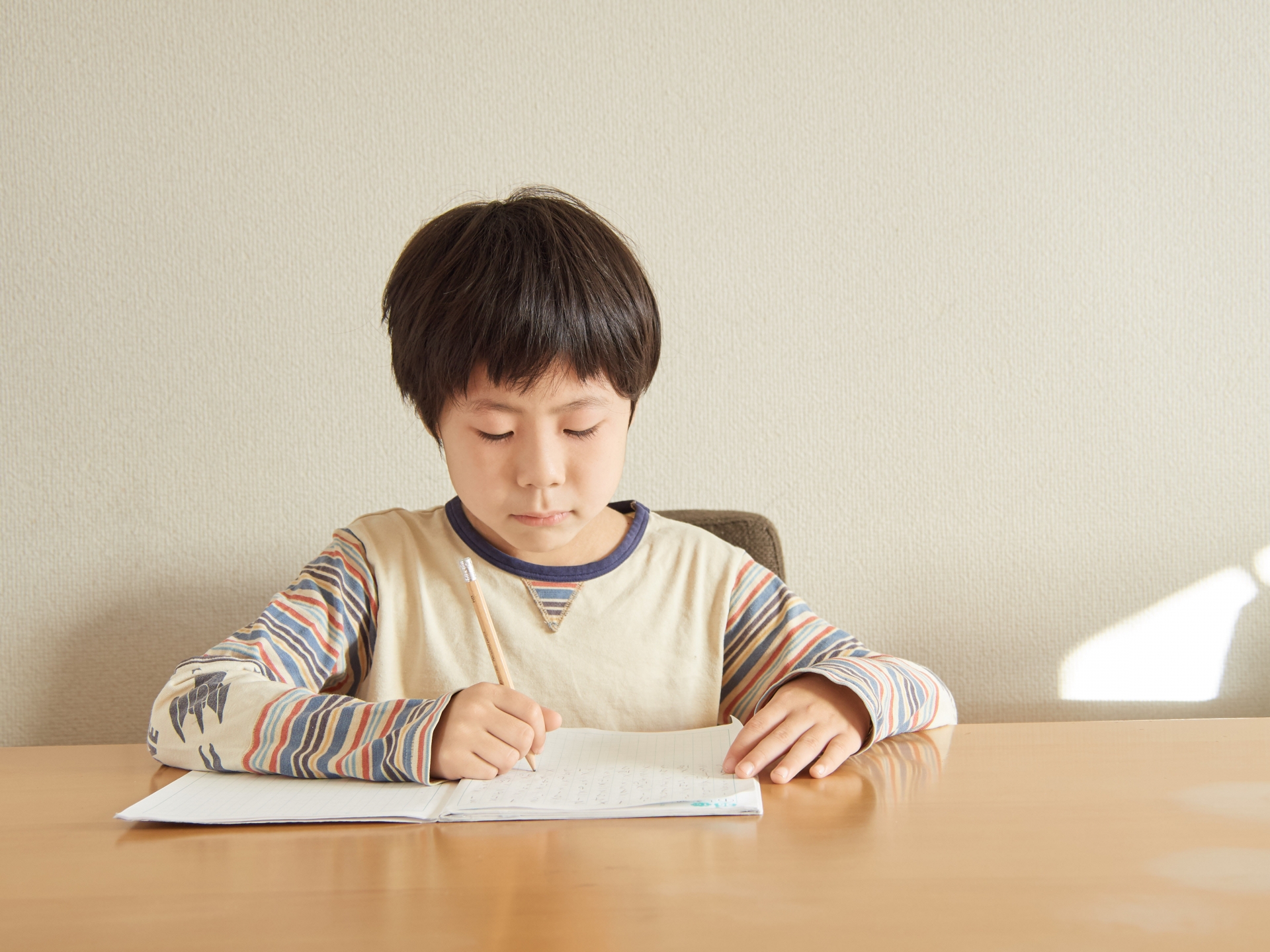

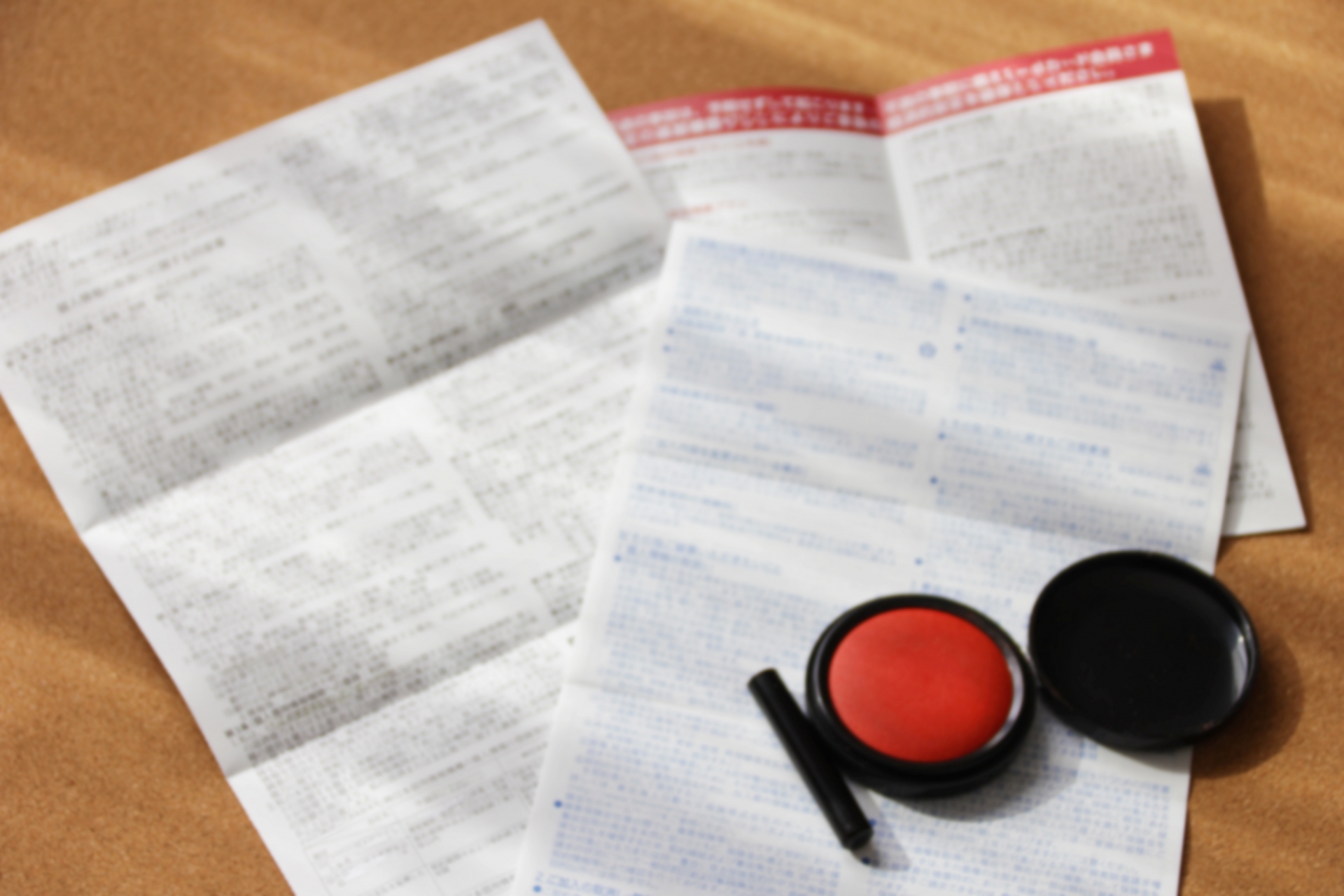














コメントを残す